reCare道玄坂鍼灸院:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-14-9 ソシアル道玄坂501
渋谷マークシティから徒歩30秒 駐車場:無
第33回はり師きゅう師国家試験
きゅう理論 解答&解説
解説
1.誤り
夾雑物(茎や葉脈などの不純物)が多い艾は粗悪で、燃焼が不均一になり温度調整が難しい。透熱灸には純度の高い艾が適します。
2.誤り
灰分が多い=燃えたあとに灰が多く残る=精製度が低い艾。
透熱灸では、灰分が少なくきれいに燃える上質な艾が望ましいです。
3.正解
精油成分が多いほど燃焼温度が高く、熱刺激が強くなる。
透熱灸ではこの高い熱刺激を利用して治療効果を狙うため、精油成分が多い艾を使用します。
4.誤り
黒褐色の艾は精製が不十分で水分や夾雑物を多く含み、燃焼性が悪い。
透熱灸に使うのは、黄白色で柔らかく精製度の高い艾です。
まとめ
透熱灸用の艾=精油成分多い/灰分少ない/夾雑物少ない/黄白色で柔らかい
粗悪艾:青臭い、手触りが悪く固い、線維が粗い、夾雑物が多い、黒褐色、煙と灰が多い、熱感が強い(燃焼温度が高い)、燃焼時間が長い、湿気を帯びている、など
解答:3
問題 172
艾を使用しないのはどれか。
1. ビワの葉灸
2. ショウガ灸
3. 押 灸
4. 紅 灸
解説
1.誤り
ビワの葉の上に艾をのせて燃やす灸法。
ビワの葉の薬効(鎮痛・抗炎症作用など)と熱刺激を併用するため、艾を使用します。
2.誤り
生姜の輪切りの上に艾をのせて燃やす灸法。
生姜の温熱・発汗作用を利用して、艾の熱が穏やかに伝わるのが特徴です。
したがって艾を使用します。
3.誤り
点火した艾柱を火が消える直前に取り除き、指などで軽く押さえる灸法。
艾を燃やすことで熱を与えるので、艾を使用します。
4.正解
紅灸は電熱・化学反応などを用いて温熱刺激を与える方法で、
艾を燃やさない=艾を使用しない灸法です。
現代的な温熱療法の一種です。
まとめ
ビワの葉灸/ショウガ灸/押灸は、隔物灸で用いられる。
隔物灸は、艾炷と皮膚の間に物を置いて施灸する方法である。塩灸、韮灸、墨灸、ニンニク灸、味噌灸、生姜灸、ビワの葉灸、押灸など。
紅灸は、薬物灸に該当する。薬物灸は、艾を使用せず、薬物を塗布して刺激を皮膚に加える方法ある。紅灸、うるし灸、油灸、硫黄灸など。
解答:4
問題 173
透熱灸を行う上で最も注意が必要なのはどれか。
1. 低血圧症
2. 骨粗鬆症
3. 糖尿病
4. 月経困難症
解説
1.誤り
低血圧では一時的に立ちくらみや倦怠感が出ることがありますが、
透熱灸の禁忌や特別な注意にはあたりません。
一般的な体調管理に留意すれば施灸可能です。
2.誤り
骨が脆い状態ですが、灸刺激が骨に直接影響することはないため、
通常の皮膚刺激では大きな問題になりません。
(ただし体位や姿勢に配慮は必要)
3.正解
糖尿病では末梢循環障害や感覚鈍麻が生じやすく、
熱刺激に対する感覚が鈍くなるため、火傷のリスクが高い。
透熱灸のような直接灸は禁忌または慎重適応です。
ポイント:感覚鈍麻+創傷治癒遅延=火傷・感染リスク大
4.誤り
むしろ温熱刺激が有効なこともあり、施灸の禁忌ではない。
腹部や腰部に行うことで鎮痛・血行促進を目的とします。
解答:3
問題174
透熱灸を最も避けるべき経穴はどれか。
1.陽 白
2.陽 谷
3.陽 池
4.陽交
解説
鍼灸の禁忌部位がテーマの問題
禁忌部位
鍼:新生児の大泉門、外生殖器、臍部、眼球、急性炎症の患部など
※肺、胸膜、心、腎、中枢神経系、大血管などへの刺鰄は注意が必要
灸:顔面、化膿を起こしやすい部位、浅層に大血管がある部位、皮膚病患部などへの直接灸など
上記内容から、
1.正解
陽白は、透熱灸を最も避けるべき経穴である。なぜなら、顔面は、体の他の部位に比べて皮膚が薄く、灸痕が非常に目立ちやすいため。
陽白は、頭部、眉の上方1寸、瞳孔線上に位置する。
2.誤り
陽谷は、手関節後内側、三角骨と尺骨茎状突起の間の陥凹部に位置する。
3.誤り
陽池は、手関節後面、総指伸筋腱の尺側陥凹部、手関節背側横紋上に位置する。
4.誤り
陽交は、下腿外側、腓骨の後方、外果尖の上方7寸に位置する。
解答:1
問題175
有痕灸施術部の消毒で最も適切なのはどれか。
1. 清拭圧は強めで行う。
2. 施灸前後に行う。
3. 施灸部を往復するように拭く。
4. 次亜塩素酸ナトリウムを用いる。
解説
1.誤り
強い圧で拭くと皮膚を傷つけたり感染のリスクを高めるため不適切。
消毒は軽い圧でやさしく一方向に拭くのが原則です。
2.正解
有痕灸(皮膚に灸痕を残す透熱灸など)は感染予防が最重要。
施灸前:皮膚の清潔保持
施灸後:創部の二次感染防止
両方での消毒が必要で最も適切。
3.誤り
往復拭きは汚染を再び塗り広げる恐れがあるため不適。
正しくは一方向に一拭きごとに面を変えるように行う。
4.誤り
これは器具や環境の消毒には有効ですが、
皮膚への使用は刺激が強く組織障害を起こすため不適。
皮膚には消毒用エタノールやヨードチンキなどを使用します。
解答:2
問題 176
熱刺激情報の伝導路はどれか。
1. 外側皮質脊髄路
2. 外側脊髄視床路
3. 腹側脊髄視床路
4. 外側網様体脊髄路
解説
1.誤り
外側皮質脊髄路は、随意運動の伝導路である。
外側皮質脊髄路 (錐体路・運動)は、大脳皮質—放線冠—内包後脚—中脳の大脳脚—橋縦束―延髄で錐体交叉—脊髄の側索である。
2.正解
外側脊髄視床路は、熱刺激情報の伝導路である。
・外側脊髄視床路(温痛覚・粗大触圧覚)は、感覚神経→脊髄後角→(交叉)→脊髄側索→視床→後脚→大脳皮質体性知覚野である。
3.誤り
腹側脊髄視床路(前脊髄視床路:粗大な触覚・圧覚)は、感覚神経→脊髄後角→(交叉)→脊髄前索→視床→後脚→大脳皮質体性知覚野である。
4.誤り
外側網様体脊髄路とは、脳幹の網様体から脊髄へと下行する神経伝導路であり、主に姿勢の制御、筋緊張の調節、運動の協調といった、随意運動以外の運動制御に関わる「運動伝導路」である。
解答:2
問題 177
施灸局所に起こる脊髄反射について適切なのはどれか。
1. 血漿が漏出する。
2. ノルアドレナリンが関与する。
3. Aβ線維の興奮によって生じる。
4. 特異的侵害受容ニューロンが関与する。
解説
1.正解
施灸局所では熱刺激により軸索反射(局所性脊髄反射)が起こります。
このとき、末梢の知覚神経終末からサブスタンスPやCGRPなどの神経ペプチドが放出され、
毛細血管の透過性が亢進 → 血漿が漏出 → 発赤・腫脹が生じます。
局所の血漿漏出は施灸反応として適切であり、軸索反射の作用が起こるためである。
軸索反射とは、末梢神経の軸索上で起こる反射様現象である。神経末端に生じた興奮が神経の分枝に沿って逆行性に伝播する現象のことをさす。したがって、鋮刺激によりポリモーダル受容器が興奮すと、軸索反射によって受容器末端から神経伝達物質が放出され、コリン作動性神経の末梢血管に働いて(血管拡張(フレア)、膨疹(浮腫))が生じる。※神経伝達物質には(CGRP、サブスタンスP)が考えられている。
2.誤り
ノルアドレナリンは交感神経末端から放出される神経伝達物質で、
血管を収縮させる作用を持ちます。
局所の発赤・血管拡張とは逆の作用なので不適切です。
ま今回の場合、「ノルアドレナリン」ではなくヒスタミン(かゆみ)が関与する。
ヒスタミンとは、酸素が不足すると細胞から放出される「発痛物質」の1つである。また、アレルギー様症状を呈する化学物質である。組織周辺の肥満細胞や血中の好塩基球がアレルギー反応の際に分泌される。血圧降下血管透過性亢進、血管拡張作用がある。
3.誤り
「Aβ線維」ではなくC線維の興奮によって生じる。
4.誤り
「特異的侵害受容ニューロン」ではなくポリモーダル侵害受容器が関与する。
ポリモーダル受容器は、侵害受容器のひとつである。主にC線維終末にある皮膚の受容器である。特徴として、①皮膚のみならず骨格筋、関節、内臓諸器官と広く全身に分布している。②非侵害刺激から侵害刺激まで広い範囲で刺激強度に応じて反応する。③侵害刺激を繰り返し与えると反応性が増大し閾値の低下がみられる。
特異的侵害受容ニューロンとは、脊髄の後角にある神経細胞の一つであり、痛みをもたらす特定の強い刺激(侵害刺激)のみに反応し、脳に痛みの「場所」を伝える役割を担う。
解答:1
問題 178
透熱灸による炎症反応で、アナフィラキシンとして作用するのはどれか。
1. IgE
2. 補 体
3. コルチゾール
4. ヒスタミン
解説
1.誤り
IgEとは、肥満細胞や好塩基球の細胞表面に存在している。ヒスタミン遊離によりアレルギー疾患を引き起こす。生後6か月以降の乳幼児では、しばしばアトピー性アレルギー疾患の進行に伴って血清中のIgE抗体が上昇する。したがって、I型反応(即時型、アナフィラキシー型)のアレルギー反応に関与する。
2.正解
補体は、透熱灸による炎症反応で、アナフィラキシンとして作用する。
アナフィラトキシンは、免疫システムの「補体」というタンパク質が活性化された際に生まれるC3a, C4a, C5aといった断片のことである。これらは肥満細胞などに働きかけ、ヒスタミンなどを放出し、血管の透過性を高めたり平滑筋を収縮させたりすることで、炎症反応やアレルギー反応(アナフィラキシー)に関与する。
補体とは、免疫反応を媒介する血中タンパク質の一群で、動物血液中に含まれる。補体は、体内に侵入した細菌やウイルスなどの病原体を攻撃し、体内から排除する働きがある。
3.誤り
コルチゾールとは、副腎皮質で合成・分泌されるホルモンで、血糖値の上昇や脂質・蛋白質代謝の亢進、免疫抑制・抗炎症作用、血圧の調節など、さまざまな働きがある。過剰になるとクッシング症候群、不足するとアジソン病を引き起こす。
4.誤り
ヒスタミンは、施灸刺激の早期より肥満細胞から放出される。
ヒスタミンとは、アレルギー様症状を呈する化学物質である。組織周辺の肥満細胞や血中の好塩基球がアレルギー反応の際に分泌される。血圧降下血管透過性亢進、血管拡張作用がある。
解答:2
問題 179
透熱灸による反応で最も早期に起こるのはどれか。
1. ポリモーダル受容器の興奮
2. 白血球の浸潤
3. 温熱感覚の認知
4. 施灸局所の血管拡張
解説
1.正解
ポリモーダル受容器の興奮は、透熱灸による反応で最も早期に起こる。なぜなら、透熱灸による反応は、まず皮膚に加わった熱刺激が生体によって感知されることから始まるため。
ポリモーダル受容器は、皮膚などに存在する感覚受容器の一種であり、強い機械刺激、熱刺激、化学物質など、様々な種類の侵害刺激(組織を傷つける可能性のある刺激)に応答する。
2.誤り
白血球の浸潤は、炎症反応の進行に伴って起こる。なぜなら、白血球の浸潤は、透熱灸による熱刺激によって組織が損傷され、炎症反応が開始し、血管透過性が亢進して、血液中の白血球(好中球やマクロファージなど)が血管壁を通って組織間隙へと移動してくる現象であるため。
3.誤り
温熱感覚の認知は、皮膚の受容器での感知、神経信号の発生と伝達、そして脳での情報処理といった一連の神経活動が必要である。
4.誤り
施灸局所の血管拡張は、軸索反射に起こる影響である。
軸索反射とは、末梢神経の軸索上で起こる反射様現象である。神経末端に生じた興奮が神経の分枝に沿って逆行性に伝播する現象のことをさす。したがって、鋮刺激によりポリモーダル受容器が興奮すると、軸索反射によって受容器末端から神経伝達物質が放出され、コリン作動性神経の末梢血管に働いて(血管拡張(フレア)、膨疹(浮腫))が生じる。※神経伝達物質には(CGRP、サブスタンスP)が考えられている。
解答:1
問題 180
透熱灸により組織損傷部から放出される物質で、末梢性の痛覚過敏に関与するのはどれか。
1. NO
2. アドレナリン
3. アセチルコリン
4. セロトニン
解説
1.誤り
NOは、鍼刺激による皮膚の血流増加に関係する。NOとは、一酸化窒素のことで、窒素(N)と酸素(O)が結合した物質である。常温では無色・無臭の気体で、水に溶けにくく、空気よりやや重い。血管の内皮細胞から放出される物質で、血管を拡張してしなやかにして、血圧を安定させる働きを持つ。
2.誤り
アドレナリンとは、腎臓の上にある副腎髄質で合成・分泌されるホルモンである。主な作用は、心拍数や血圧上昇などがある。自律神経の交感神経が興奮することによって分泌が高まる。
3.誤り
アセチルコリンとは、代表的な神経伝達物質であり、①運動神経の神経筋接合部、②交感神経および副交感神経の節前線維の終末、副交感神経の節後線維の終末などのシナプスで放出される。アセチルコリンは、中枢神経で働く場合と末梢神経で働く場合で作用が異なる。①運動神経の神経筋接合部では、筋収縮に作用する。
4.正解
セロトニンは、透熱灸により組織損傷部から放出される物質で、末梢性の痛覚過敏に関与する。なぜなら、ケミカルメディエーターであるため。
セロトニンとは、主に脳幹縫線核由来の中枢神経伝達物質で、うつ病と関連が深い神経伝達物質である。気分・睡眠・痛み調節などに関与する。交感神経を刺激し、血圧を上昇させる作用がある。
ケミカルメディエーターとは、化学伝達物質ともいい、細胞間の情報伝達に作用する化学物質のことである。肥満細胞が放出するケミカルメディエーターは、さまざまなアレルギー反応(血管透過性の亢進、血流の増加、炎症細胞の遊走など)を起こす。
【例】
・ヒスタミン
・ロイコトリエン
・トロンボキサン
・血症板活性化因子
・セロトニン
・ヘパリンなど。
解答:4
【監修者】 鍼灸学博士 納部瑠夏
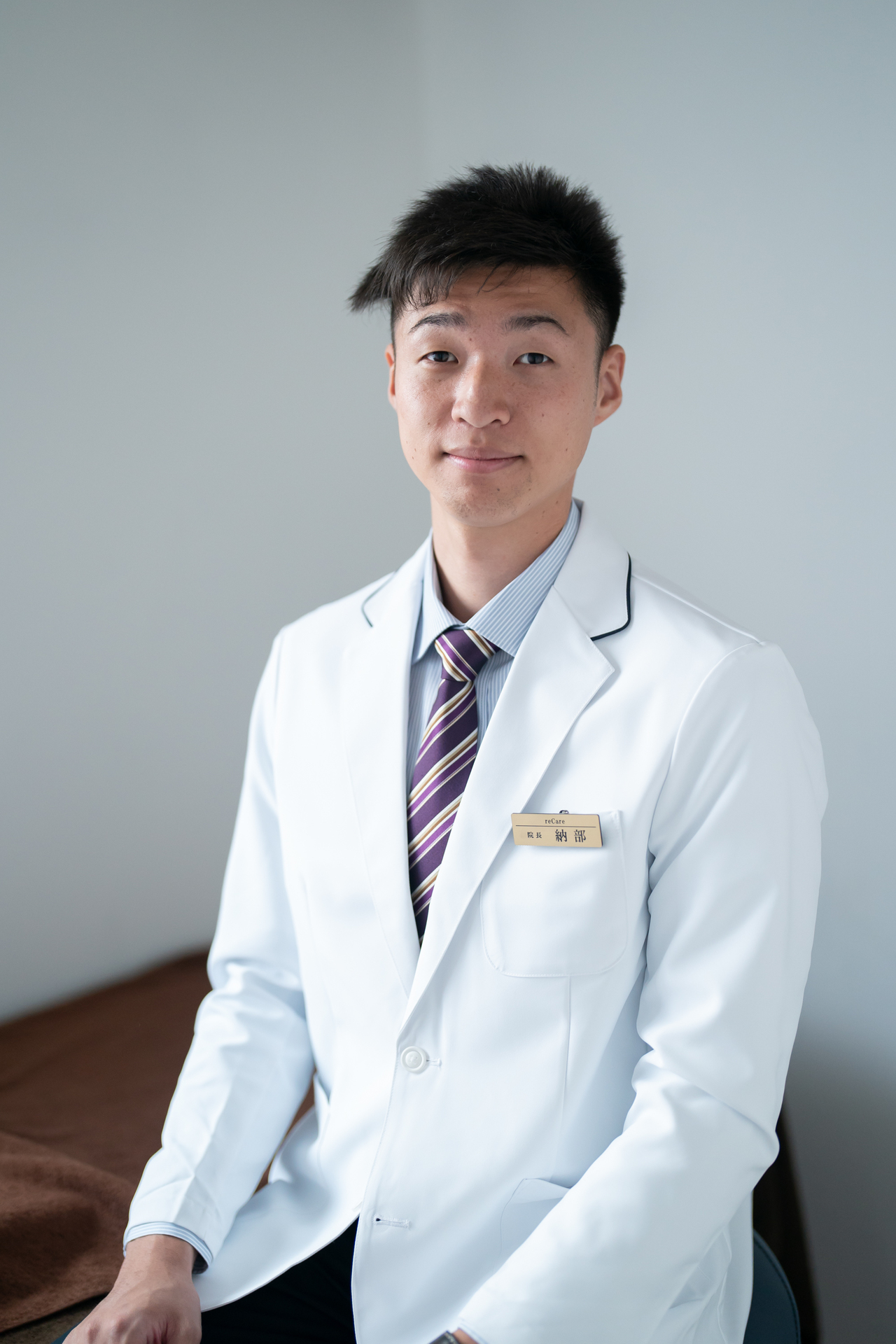
鍼灸系の大学院を修了し、鍼灸治療の専門家の証である「鍼灸学博士」を保持。
reCare道玄坂鍼灸院の院長として臨床を行う傍ら、福岡リゾート&スポーツ専門学校で非常勤講師として教鞭を行っている。
保有資格
鍼灸学博士、はり師・きゅう師、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー、健康運動実践指導者
主な研究業績
【共同執筆者】
今西 好海
保有資格 鍼灸学修士、はり師・きゅう師、健康運動実践指導者
奈須 守洋
保有資格 鍼灸学修士、はり師・きゅう師
reCareラボ
-
- 科目ごとの解説
-
- 鍼灸国家試験過去問の解答&解説