reCare道玄坂鍼灸院:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-14-9 ソシアル道玄坂501
渋谷マークシティから徒歩30秒 駐車場:無
第32回はり師きゅう師国家試験
東洋医学臨床論 解答&解説
1:小脳出血の症状
2:頭蓋内圧亢進により出現する症状
3:群発頭痛の症状
4:急性副鼻腔炎の頭痛
解答:3
1:小頬骨筋・大頬骨筋
2:小頬骨筋
3:咬筋
4:上唇鼻翼挙筋・上唇挙筋・小頬骨筋
解答:1
Z変形は、母指の中手指節関節に生じる変形。
1:魚際→第一中手骨中点の橈側、赤白肉際
2:二間→示指、第二中手指節関節橈側の遠位陥凹部、赤白肉際
3:少沢→小指、末節骨尺側、爪甲角の近位内方1分
4:中渚→手背、第4・第5中手骨間、第4中手指節関節の近位陥凹部
これらの4つの経穴のうち、母指に位置するのは1の魚際
解答:1
1:第5腰椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方1寸5分
2:臍中央の下方3寸、上前腸骨棘の内方
3:第2腰椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方3寸
4:第3後仙骨孔の位置
脊髄に存在する排尿中枢は、仙髄です。これらの経穴のうち、仙骨神経の支配領域に存在する経穴は4の中髎です。
解答:4
C6-C7頚椎間から出る神経は第7頚神経です
1:前腕橈側から母指を支配するのは第6頚神経
2:手背中央から中指を支配するのは第7頚神経
3:小指球から小指を支配するのは第8頚神経
4:前腕尺側を支配するのは第8頚神経
解答:2
解き方
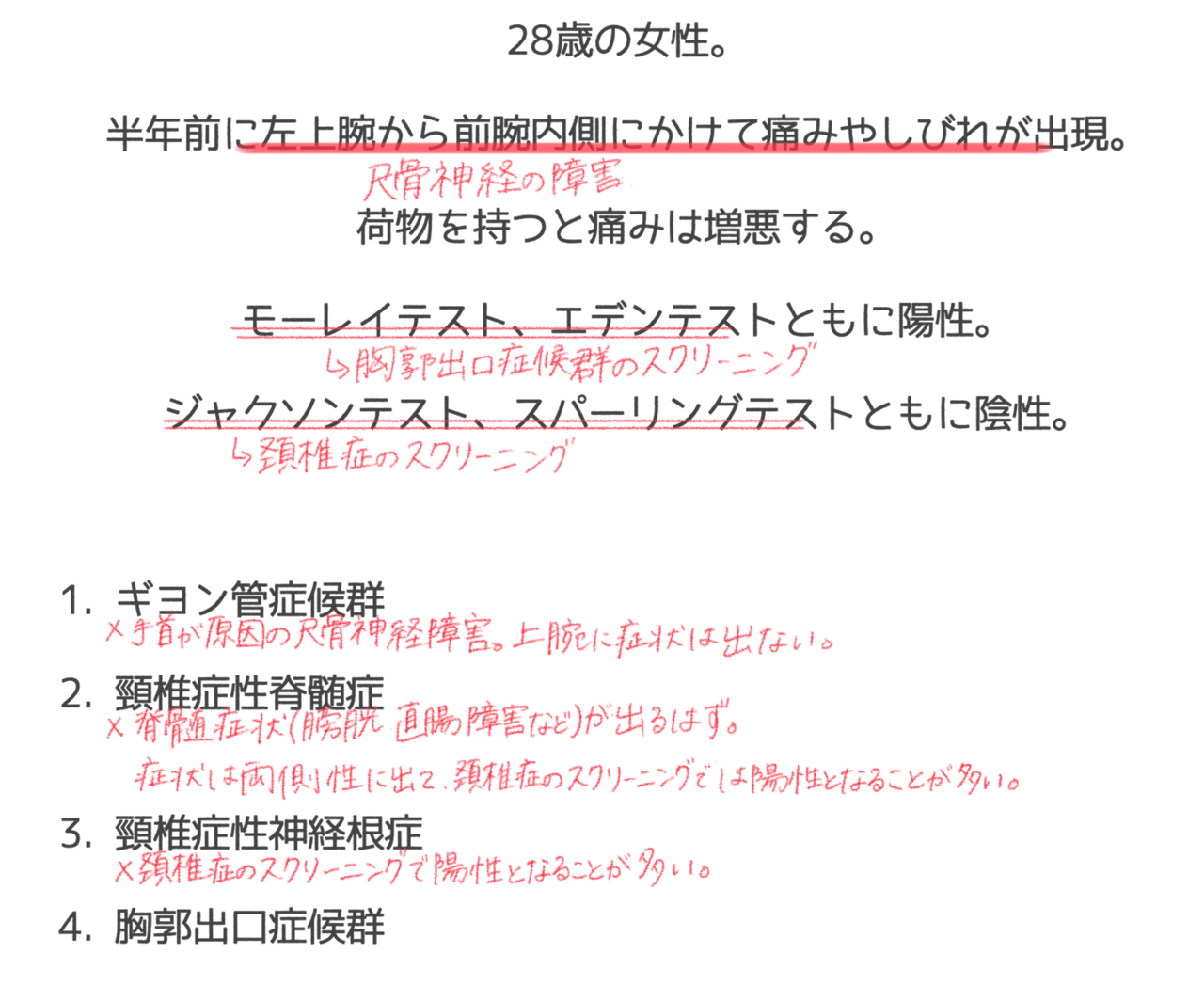
解答:4
解き方の例
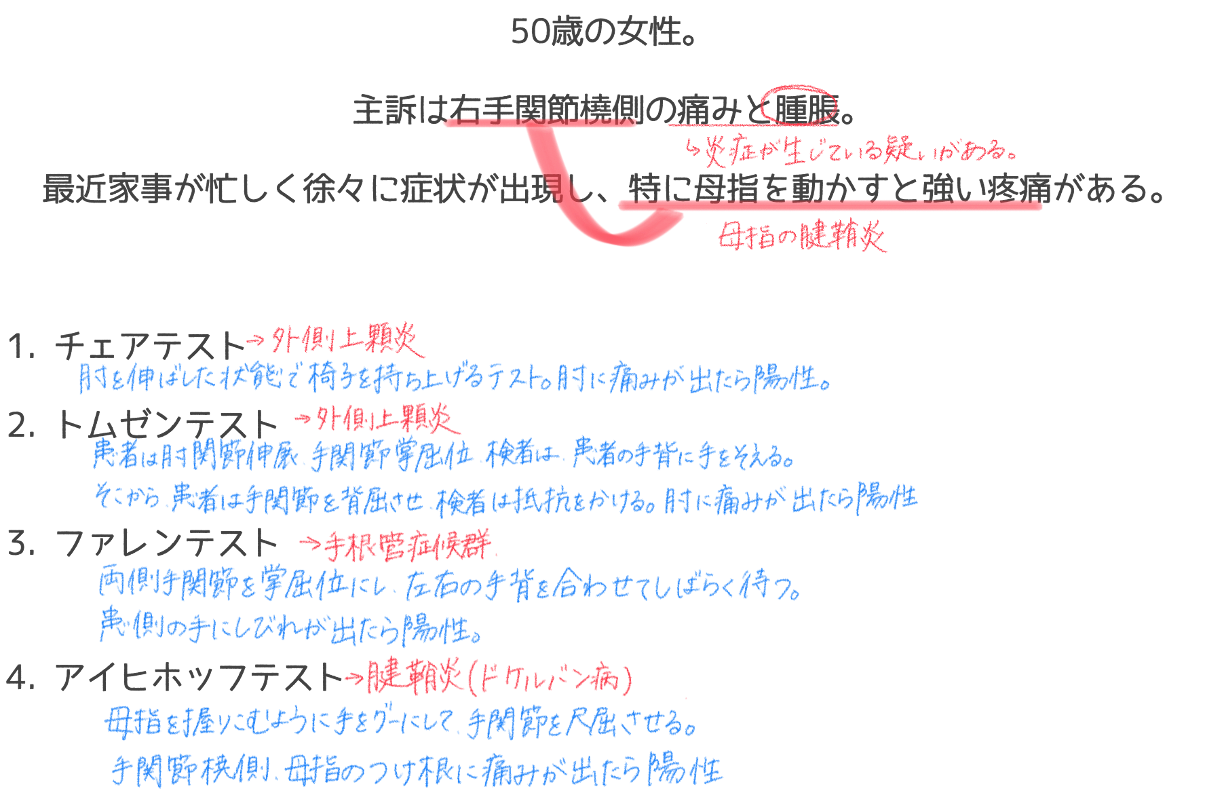
解答:4
1:L3→腱反射なし
2:L4→膝蓋腱反射
3:L5→腱反射なし
4:S1→アキレス腱反射
解答:4
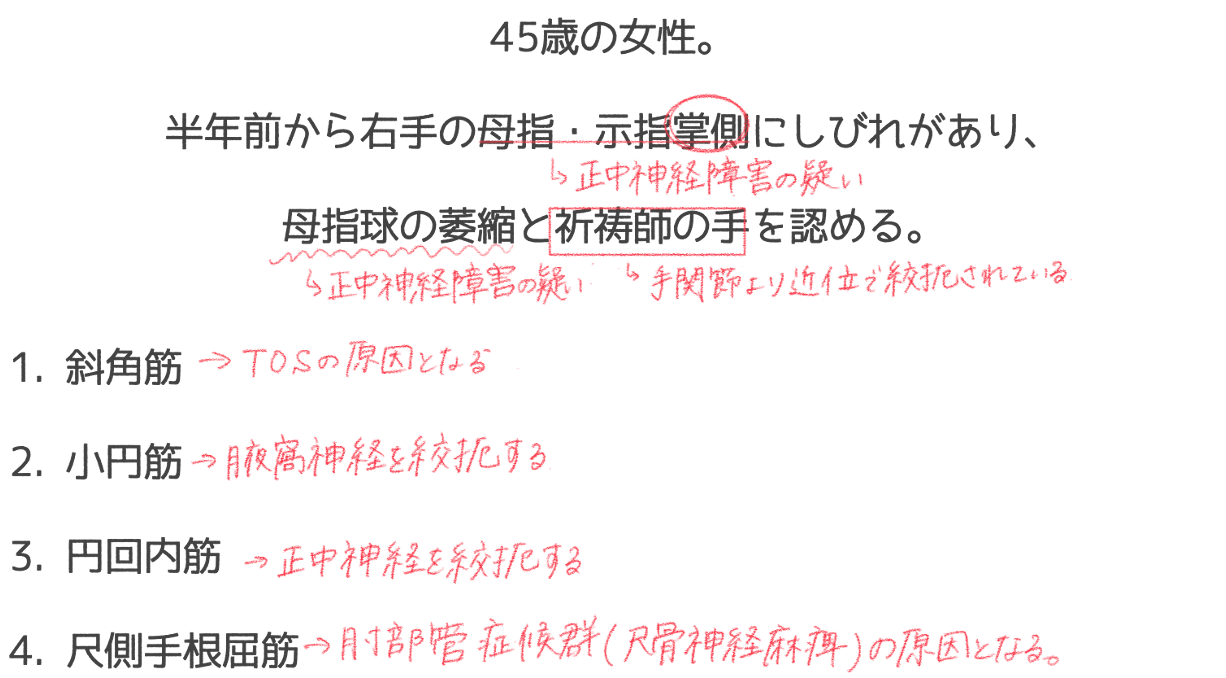
解答:3
パテラセッティングとは、仰臥位で寝た状態で膝下にタオルなどを置き、膝を伸ばしてタオルを床に押し付ける運動です。大腿四頭筋と膝窩筋を鍛えるトレーニングです。
1:委中→深部に脛骨神経が通る
2:承扶→大殿筋
3:風市→腸脛靭帯、大腿二頭筋長頭
4:膝陽関→腸脛靭帯、大腿二頭筋長頭腱
解答:3
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ン
解答:2
動作緩慢、丸薬丸め運動は、パーキンソン病/パーキンソン症候群の特徴的な症状です。
この病気では、受動運動に対し、関節の歯車様または鉛管様の抵抗が見られます。
解答:2
1. 禾髎 ---- 口輪筋
2. 瘈脈 ---- 後耳介筋
3. 下関 ---- 咬筋・外側翼突筋
4. 懸顱 ---- 側頭筋
解答:3
改訂長谷川式簡易知能評価スケールの項目
- 年齢
- 日付に関する見当識
- 場所に関する見当識
- 言葉の記銘
- 計算
- 逆唱
- 言葉の遅延再生
- 物品再生
- 言葉の流暢性
MMSEの項目
- 時間に関する見当識
- 場所に関する見当識
- 聴覚言語記銘
- 注意と計算
- 再生
- 呼称
- 復唱
- 理解
- 読字
- 書字
- 描画
解答:2
後骨間神経とは、前腕を支配する橈骨神経から肘の辺りで枝分かれして、回外筋や指を伸展させる筋肉を支配している。この神経が圧迫や損傷を受けると、指が伸ばせずに垂れ下がった状態になるので正解は3.下垂指である。
解答:3
三叉神経第2枝は、鼻の下、上唇から頬やこめかみにかけての領域を支配する。
1.曲差、2.陽白は三叉神経第1枝の支配エリアにある。
4.大迎は三叉神経第3枝の支配エリア。
解答:3
六部定位脈診では、右手寸口の沈は手の太陰肺経が配当されているので、上記の場合は肺虚症を考える。また難経六十九難の治療法では、「虚すればその母を補い、実すればその子を瀉せ」という考えに基づき、臓腑と経絡の五行の性格を用いて補瀉すべき治療穴を選穴する。
肺虚症には自経(肺経)の母性穴(土穴)である太淵、母経(脾経)の母性穴(土穴)である太白を用いる。
解答:1
解説
1.誤り
落沈は、手背、第2・3中手指節関節の間の近位陥凹部に取る。別名は、外労宮という。【主治】寝違えである。
2.誤り
胆嚢点は、陽陵泉(胆)の下約1寸に取る。【主治】胆嚢炎、胆石症、胸脇痛、下肢痛、下肢運動麻痺である。
ちなみに、陽陵泉は、下腿外側、腓骨頭前下方の陥凹部に位置する。
3.誤り
腰痛点は、手背、第2・3および第4・5中手骨底間の陥凹部の2点に取る。別名は、腰腿点という。【主治】急性腰痛、捻挫、腱鞘炎、リウマチ
4.正解
足背痛に対する八風は、取穴部位が主治症の局所にある奇穴である。
八風は、足背、各中足指節関節の間に取る。【主治】足の痛み(脚気、足背痛、足指の発赤・腫張、関節リウマチ)
解答:4
解説
本症例のポイント
・56歳の男性。
・職場の人間関係のストレスから不眠、動悸。
・最近:物忘れや腰下肢の重だるさ、歯のぐらつき。
・舌質:紅、脈:数。
→本症例は、心腎不交が疑われる。心火が亢進しすぎて不眠となり、また心火の亢進から心腎不交となり、腎陰が損耗し、心陰を補えない状態のことである。
1.誤り
肝血虚は、目乾、目花、転筋、しびれ、不眠、多夢、脈細、舌質淡白などがあげられる。
2.誤り
腎陽虚は、腰膝酸軟、冷え、畏寒、陽萎、不妊、泄瀉、夜間尿、舌苔白などがあげられる。
3.正解
心火を除く。心腎不交とは、腎陰が損耗し、心陰を補えず、心火が亢進しすぎて不眠を生じる状態のことである。
4.誤り
肝陽上亢とは、眩暈、耳鳴、頭痛、目赤、陰虚によるほてり・のぼせ、腰膝酸軟などである。
解答:3
解説
右足第1趾と第2趾に痛み → 足の厥陰肝経(第1趾)と足の太陰脾経(第1趾〜第2趾内側)の経脈領域に関係します。
ここで「表裏する経脈を同時に治療」という条件がポイントです。
表裏関係の経絡は、問題のツボから脾経は胃経、肝経は胆経と表裏の関係にある。
| 選択肢 | 経絡 | 穴の種類 | 部位・作用 |
|---|---|---|---|
| 1. 行間 | 肝経 | 滎穴 | 熱をさまし、肝気を調える(肝経単独) |
| 2. 公孫 | 脾経 | 絡穴・八脈交会穴(衝脈) | 胃経(表裏)にも影響する。脾胃を同時に調える |
| 3. 衝陽 | 胃経 | 原穴 | 胃経の原気調整。胃単独への作用が強い |
| 4. 中都 | 肝経 | 郄穴 | 急性の肝経症状に使用(肝経単独) |
上記の中で、絡穴は2の公孫だけである。絡穴は他の経脈との交流部としての働きもあるので、表裏関係の胃経ともつながる。
よって答えは2の公孫
解答:2
解説
テーマは「足の陽明胃経の経脈病証」。
経脈病証とは、その経脈に沿って起こる症状のことです。
足陽明胃経の走行と特徴
起始部:鼻翼の外側(迎香)
上行:目の下 → 顂 → 口角 → 下顎 → 頸部 → 鎖骨下
下行:腹部 → 大腿前面 → 下腿前面 → 足背 → 第2趾外側端(厲兌)
したがって、顔面・口周囲・消化器系・下肢前面に症状が現れます。
| 選択肢 | 経脈・病証 | 説明 |
|---|---|---|
| 1. 口が歪む | 足陽明胃経 | 経脈病証そのもの。顔面麻痺・口喎に相当。 |
| 2. 口が苦い | 手少陽三焦経・足少陽胆経 | 少陽病証(肝胆系)。 |
| 3. 口が乾く | 足厥陰肝経 | 厥陰肝経の病証 |
| 4. 口が熱い | 胃熱証(臓腑病証) | 経脈病証ではなく臓腑病証。 |
上記より1の口が歪むが正解
解答:1
解説
・45歳の男性。
・仕事のストレスでのぼせ感が続く。
・最近:イライラして気持ちがたかぶり眠れない日が多くなっている。
・舌尖:紅、脈:数、有力を認める。
→熱があるときに使用される十二刺を選択しよう。
1.正解
輸刺は、本病証に対する十二刺である。
輸刺は、 気が盛んで熱があるとき、真っ直ぐ深く刺し、真っ直ぐに抜く。
2.誤り
陰刺は、寒厥のとき、左右の太渓穴に同時に刺入する。
3.誤り
斉刺とは、寒気・痹気の範囲が狭く深部のとき、中心とその両側に刺す方法である。3本使用する。
4.誤り
揚刺とは、寒気の範囲が広く大きいとき、その中心と、四隅から中心に向かって刺す方法である。5本使用する。
解答:1
解説
1.誤り
血虚は、眩暈、顔面蒼白、動悸、不眠、健忘、目のかすみ、しびれ、痙攣、月経痛、経少、経色淡白、視力減退、爪の変形などである。
2.誤り
陰液とは、陰に属する血・津液・精をまとめた呼称である。気は陽に属する。陰虚に対し行う。
3.正解
気の病証のひとつである痰湿(津液の停滞)は、湿・水:(身体が重だるい、浮腫、下痢)など、飲:腹鳴、動悸、喘息、浮腫など、痰:眩暈、咳嗽、頭痛、動棒、意識障害、精神障害などの状態をいう。
4.誤り
瘀血(おけつ)とは、血液が汚れたり、滞ったり、固まりやすくなった状態のことである。瘀血になると、血の流れが悪くなり、全身に栄養が行き渡らなくなるため、さまざまな症状が現れやすくなる。
解答:3
解説
1.誤り
胃火上炎は、胃熱の症状、頭痛、咽頭痛、口内炎がみられる。
2.正解
津液不足は口唇・咽喉などの乾き、皮膚・髪などの乾燥、尿量減少、乾燥便などがみられる。
3.誤り
肝の生理として、疏泄(情志・気機・月経の調節、脾胃の補助)がみられる。
4.誤り
膀胱湿熱として、頻尿、尿意促迫、隆閉、排尿痛、血尿、小便短赤、舌質紅、脈滑数などがみられる。
解答:4
解答:2
【監修者】 鍼灸学博士 納部瑠夏

鍼灸系の大学院を修了し、鍼灸治療の専門家の証である「鍼灸学博士」を保持。
reCare道玄坂鍼灸院の院長として臨床を行う傍ら、福岡リゾート&スポーツ専門学校で非常勤講師として教鞭を行っている。
保有資格
鍼灸学博士、はり師・きゅう師、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー、健康運動実践指導者
主な研究業績
【共同執筆者】
今西 好海
保有資格 鍼灸学修士、はり師・きゅう師、健康運動実践指導者
奈須 守洋
保有資格 鍼灸学修士、はり師・きゅう師
reCareラボ
-
- 科目ごとの解説
-
- 鍼灸国家試験過去問の解答&解説